バンド練習中、こんな経験ありませんか?
「次、この場所をもう一回!」
「え、どこ?」
「サビの前のとこ!ラララって歌ってるところ!」
……言っている本人は伝えているつもりでも、意外と伝わらない。
この記事では、バンド内のやり取りがスムーズになるようなセクション名の伝え方について、日本語と英語の対応関係と各セクションの役割、さらにSALT流の記譜ルールをご紹介します。
セクション名の日本語・英語対応と役割まとめ
以下は、日本語・英語表・役割を一覧にしたセクション名対応表です。
| 日本語表記 | 英語表記 | 役割・定義 |
|---|---|---|
| イントロ | Intro | 曲の導入。主に楽器中心。ボーカルが入ったらAメロとみなすことが多い。 |
| Aメロ | Verse | 曲の世界観・物語の導入。メロディは控えめでサビとの対比をつくる。 |
| Bメロ/前サビ | Pre-Chorus | サビへの助走。コードやリズムに変化があり、緊張感や期待を高める。 |
| サビ(Cメロ) | Chorus | 曲の中で最もキャッチーで繰り返されるパート。感情の中心。 |
| 間奏 | Interlude / Instrumental | 楽器のみのパート。展開・ブレイク・流れの切り替えに使われる。 |
| ソロ | Solo / Instrumental Break | ギター等が主役となる演奏パート。技巧の見せ場。 |
| 落ちサビ | Quiet Chorus / Breakdown | 静かなサビ。ソロ後やラストサビ前に入ることが多く、緩急をつける。 |
| Dメロ(大サビ) | Bridge / Climax / Final Verse | 展開部。1回のみ登場し、サビ以上の盛り上がり(大サビ)になることも。 |
| ラストサビ | Final Chorus / Last Chorus | 曲の最後に登場するサビ。転調など、感情のピークになる。 |
| アウトロ | Outro / Ending | 曲の締め。ボーカルが入っていても終末感があればアウトロとみなす。 |
補足:「歌い始めたらイントロじゃないの?」→ ボーカルが歌い始めてもイントロと解釈する場合もありますが、ボーカルが入った瞬間からAメロとするのが一般的です。
バンド練習で伝わるセクション名の呼び方
バンドで「次そこ合わせよう!」と言うとき、ありがちな伝わらないパターンと、伝わりやすい方法を紹介します。
×例①「スコアのリハーサルマークFから!」
→ 全員が同じ楽譜を共有していれば伝わるが、メンバーが違う楽譜を使っていたり、暗譜・自作譜の場合、伝わらない。
×例②「ラララって歌ってるところ!」
→ 雰囲気は通じることもあるけど、曖昧で伝わらない場合も。
◯例③「2番のAメロ5小節目が合わないので2番Aメロ頭から!」
→ 曲の構成が全員に共有できていれば、セクション名が一番明確に伝わる。歌詞も伝えうとより伝わりやすい。SALTはこの方法を推奨しています。
SALT流:セクション名記譜ルール
- 「番号+日本語」で記載(例:1Aメロ、2Bメロ、3サビ)
- 間奏・ソロなどはそのまま記載(例:ソロ、間奏)
- 特殊な箇所には(ラストサビ)(大サビ)など補足を追加
- ルールに縛られすぎず、伝えること(演奏者が理解しやすいこと)を優先
【記譜例】いきものがかり「ブルーバード」構成
【冒頭サビ】→【間奏①】
【1Aメロ】→【1Bメロ】→【1サビ】→【間奏②】
【2Aメロ】→【2Bメロ】→【2サビ】→【ギターソロ】→【Dメロ】
【3サビ(ラストサビ)】→【アウトロ】※このように番号とセクション名をセットで記載します。この構成をバンド内で共有しておけば、意思疎通がしやすいです。
まとめ
- 「1番Aメロ」「2番Bメロ」「3番サビ」などで伝えれば、バンド内の意思疎通がスムーズに。
- 英語表記との対応関係も押さえておくと、英語表記で記載された楽譜を見る時に理解できる(Verse = Aメロなど)。
- 曖昧になりやすい「落ちサビ」「Dメロ」などの用語は、バンド内で共通認識を作ることが重要。
- セクション名記譜の目的は、“伝えること”。伝わるなら多少のアレンジも問題ない。
- 僕自身も、販売中の楽譜をより伝わりやすくするため、記譜方法を随時アップデートしていきます。
あなたのバンド練習にも、分かりやすい譜面を
本記事でご紹介したような「伝わるセクション名」を意識して、僕自身も見やすさ・わかりやすさ重視の楽譜を制作・販売しています。

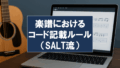
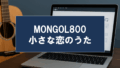
コメント
クオリティ高い セクションの一貫性。